
黒川城→若松城→鶴ヶ城
福島県内では鶴ヶ城の愛称で親しまれていますが、今から約630年ほど前に、その前身ともいえる東黒川館を葦名直盛が築いたのがはじまりと言われています。
以後、代々蘆名氏の城でしたが、1589年(天正17年)、蘆名氏と戦いを繰り返していた伊達政宗が蘆名氏を滅ぼし黒川城を手にしました。
その後も城主は変わり、蒲生氏郷、上杉景勝、加藤嘉明らが城の主となりますが、1643年に保科正之(のちに松平氏)に入場すると、以降は松平家が城主として君臨しました。
幕末の戊辰戦争では、約1ヶ月に及ぶ激しい攻防戦に耐えましたが、明治7年に取り壊されました。
昭和40年に再建され、平成13年には天守閣に続く「干飯櫓・南走長屋」が江戸時代の工法・技術を用いて復元されています。
平成23年には赤瓦へふき替え、幕末当時の姿を再現しています。


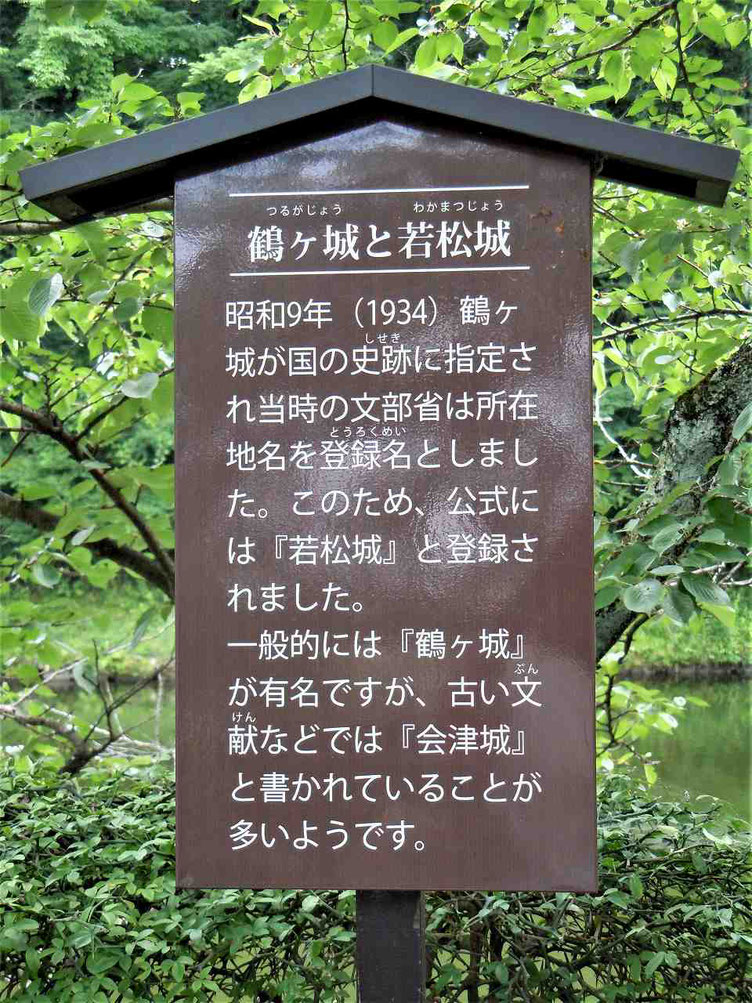


難攻不落の名城
戦国時代からつづく、難攻不落の城といわれた鶴ヶ城は、戊辰戦争では1カ月間にわたる攻防の末にも落ちませんでした。
戦のために作られた城であることから、城に続く道にもさまざまな仕掛けがあります。





敵を三方から攻撃できる枡形と呼ばれる石垣。


会津地震で倒壊した天守を現在の形に組みなおす
鶴ヶ城という名前になったのは、蒲生氏郷が望楼型7重の天守にしたことから。
鶴が舞うような城という意味でしょうか。
蒲生氏郷時代の石垣の基底部が発掘、確認され、鬼瓦をはじめとする瓦の一部に金箔が貼られたものが出土しています。
かなり豪奢なお城だったようです。
しかし、1611年(慶長16年)に起きた会津地震によって天守は倒壊。
その後、倒壊した天守を今日のような層塔型天守に組みなおしています。
ちなみに、このときの会津地震とは、震源を大沼郡三島町滝谷付近とする直下型地震で、マグニチュード6.9、震度6強から7と推測されている大地震でした。







月見櫓
武器庫として利用された櫓ですが、この櫓にかかる月が美しかったことで、月見櫓と呼ばれています。

茶壺櫓
茶室「麟閣」の裏側にある櫓で、茶道具類がおさめられていたそうです。

「荒城の月」
土井晩翠が作詞した「荒城の月」は、戊辰戦争後の鶴ヶ城と青葉城をモデルに書いたと伝わります。
茶室「麟閣」
千利休の子・少庵が建てたと言われる茶室「麟閣」。
戊辰戦争後、城下に移築され保存されていましたが、平成2年に元の場所である鶴ヶ城内へ移築復元されました。








御三階跡(おさんがいあと)
鶴ヶ城には、御三階と呼ばれる高層建築物がありましたが、現在は、阿弥陀寺に移築されています。


鶴ヶ城内は公園として整備されています。
天守閣と麟閣は有料です。
戦国武将に扮した案内役の方も複数いて、写真撮影にも応じてくれます。
武道場も併設されており、運が良ければ、長刀の稽古風景を見ることができます。
干飯櫓・南走長屋
平成13年に江戸時代の工法でつくられた干飯櫓・南走長屋は、土産物売り場と見学コースに分かれています。





桜の名所
鶴ヶ城は、桜の名所でもあります。
明治時代に植えられた多くの桜が、鶴ヶ城全体を包みます。





甲賀町口門跡
この門を境に、内側を侍屋敷、外側を町民としました。
郭内と郭外の間には、土塁が築かれ、外濠がめぐらされていました。
この甲賀町口門は、大手門として、特に厳重な構えをとっていました。



| 「透けない」「破れない」「肌にやさしい」女性のための 温泉着 湯浴み着 | ||||
|
| バリアフリー温泉で家族旅行 (温泉ガイド) | ||||
|
| ふくしま日帰り温泉気ままに100湯 | ||||
|
| 温泉の科学 温泉を10倍楽しむための基礎知識!! (サイエンス・アイ新書) | ||||
|
| 映画 クレヨンしんちゃん 爆発!温泉わくわく大決戦 同時収録 クレしんパラダイス!メイド・イン・埼玉 [DVD] | ||||
|





